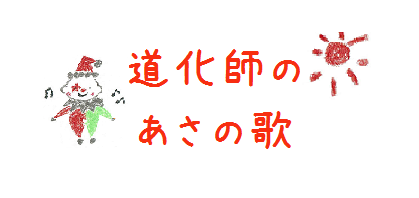なんでこんなに「書いておかないと不安」なのか…、考えても考えても「これ!」というしっくりくる理由は見つからないが、せめて書き記すことで頭の中のものを「形」にしないとなんっにもない、という思いはあった。
とにかく「考えること」だけはする。頭の中でもう疲れるくらい考えて。四六時中その事で頭がいっぱいになって。
「考えること」で、心を落ちつかそうとする。
ただ「考える」と言っても、建設的な解決策とかでは全然なく。
例えば何か嫌なことがあると、そのことが頭を離れない。
離れないというより、まるでマゾのように自分から何度も思い返す。忘れそうになったら「ダメじゃない」とばかりに再び頭に焼き付ける。
その方が心が落ち着くのだ(忘れることより)。むしろなんも考えないまま忘れる方が恐怖だった。
考えないようにして忘れても、また同じような状況が来ればまた同じことをしてしまい、きっと傷つく。それが怖い。
カッとなったり傷ついたり落ち込んだり焦ったり、感情に振り回されている状態がすごく嫌だった。嫌な感情、モヤモヤとした気持ち悪いものは今すぐ取り除かなければならない、そう考えていた。
私は精神的にも潔癖だった。
机の上に埃ひとつ、塵ひとつあるとすぐに取り除かねば気がすまないのと同じく、心の中に不快な感情…怒り、動揺、傷つき、焦り、モヤモヤがあると、それを消し去らないことには、他のことが何も手につかなかった。
再生する中で、なんで傷ついたの?なんでカッとなるの?と考える。それが自分なりのショックのやわらげ方だった。どうしてそのことが起きてしまったのか、分析して、頭の中で問題を客観視するだけで、だいぶショックがやわらぐ。
その分析を頭の中で全部言葉にする。
感情が言葉になった時点で昇華できた気分になった。
でも分析して、じゃどうしたらいいのか、それを実行することはほとんどなかったけど。
頭の中でぐるぐる格闘して、疲れるくらい思考して、もはや何か大きなことを「成し遂げた」気にすらなるけど、実際は何もしていない。何も動いていない。何も変わっていない。ただ じっとしていただけで、振り返ったら、ただの”なんっにもない”時間。
心の中のやり取りだけでどっと疲れて、ハッと我に返って気づく現実の「無」、それがすごくもどかしかった。
考えたことを、全然実行できない。だから、書く。
せっかく考えたことも、実行しなければ風前の灯火。。
抽象的な書き方ばかりではアレなので具体的なことを書くと、
高校の時の「考えていたこと」の多くは、友人Mとのこと。友人Mに対する激しい怒りだった(Mとのこと4割、ちっともやる気が戻ってこない勉強への焦りが5、残りの1割は親とのことだった)。
なんで!?どうしてあんなこと言うの!?私何かした?どうしてあんなに人をバカにするの!?
Mは高校時代から引きこもり途中まで、唯一の友人だった。
詳しくは「高校生活」のところで触れているけど、最初はとても仲が良かったけど、だんだんと互いに腹の中ではいがみ合う関係になってしまった。
なんで?とか理由を考えたり、いかにして言い返すか、どうやったらバカにされないか、頭で必死に考えて怒りを鎮めようとした。それが全部言葉になってた。今度こう言われたらこう言い返す、~だったのがいけなかったかもしれないから、今度はこうしてみよう、ああしてみよう、あれは自分は間違ってない、悪くない等々。。頭の中で言葉炸裂。
まぁ…そんなん考えても、考えたとおりにいった試しなんてほとんどなかったけど(いや、ほとんどどころかまったく…)。
頭であんなに「ああする」「こうする」と考えても、”実際の場”になると、そんな決意、いとも簡単にふっ飛んだ。
できないのだ。考えていたことを、まったく行動に移せない。頭で考えていた通りになんて全然いかない。
というかそもそも、根本的な部分に全然向き合えてなかったし。自分の何が問題なのか、それを考えられる力はあの頃まったくなかった。相手が性格悪すぎるとか、自分は優しすぎるからナメられてるんだとか(オイオイ…)、毅然とした態度を取る!とかスキを見せないとか、もう完全に的外れすぎることしか考えていなかった。
それでも何でも、頭で考えることで、すぐにでも心の切り替えをしたかった。
誰にも突っ込まれない自分の頭の中の世界に逃げ込んで、そこで表には出せない感情を爆発させ、ひとしきり暴言を吐き、自分を正当化し、自分のいいように 結論づけて、つかの間の安心を得る。
そんな自分に、無理矢理感というか、綱渡り感がどうしようもなくあった。
安心のさせ方がもろい。。
でも、現実、他人はどうにもならない。歯が立たない。だから「せめて書くことで」、そういう思いはあったと思う。
書いたら、消えずに形に残る。それが大きな安心になった。