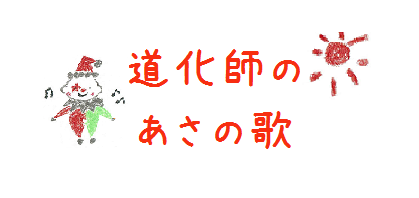強迫性障害の種のようなものは、物心ついたころにはすでにあったように思う(手がベタベタするのが気持ち悪いとか、物の位置のズレが気持ち悪くてしょうがないとか)。
それが芽を出して本格的に花開いてしまった(?)のが、小学校1年生の時だったと思う。それまで住んでいた公営住宅から新築の戸建に引越し、自分の部屋が与えられた。
この時から、”整っていないと気がすまない強迫観念”のようなものが出だしたと思う。
ある時、カーテンの山折りと谷折りの間隔が均等になっていないのが気になって、微調整を繰り返してしまうということがあった。
表のカーテンは厚地で折れ目もしっかりとしていて形を整えるのは簡単だったけど、内側のレースのカーテンが厄介だった。
レースの生地は薄く、折れ目もはっきりではなくふんわりとした程度で、「幅が均等になるよう(均等に見えるように)維持する」というのが難しい。更に、縦にストライプのように編み込まれたレースの模様が、じっと見ているとところどころ曲がって見えて、それもまた気になってしょうがなかった。
30分、1時間と、必死の形相でカーテンとにらめっこしてはカーテンの折れ目と格闘する日々が続いた。
カーテンを乗り切ったと思ったら、次はピアノカバー。
ピアノカバーには”フリンジ”と呼ばれる、マフラーの両端についているような束状の飾りがついていた。それの先がちょこっと折れ曲がっていたり隣の束と交差していたりと、きっちり平行に並んでいないのが、どーーーうしても我慢できなかったのだ。
指で1本1本引っ張ったりして整えてみるが、なかなか気の済むような真っ直ぐにはならない。長さが均一じゃないのもムズムズして仕方がなかった。
一度気になり始めると、どうにもならない。何とかしてまっすぐきれいに整えずにはいられない。
格闘の末、これはカーテンのように手で整えるのは無理だと思った。
一刻も早くこのイライラから解放されるにはどうしたらいいか考えた末、「曲がってるところ、長すぎる部分はハサミでカットすればいいんだ」という暴挙を思いついた。
フリンジは1本の線も細い何本もの糸からなっていて、切るたびにボロボロと繊維がこぼれ落ちる。ハサミを入れれば入れるほどボロボロになった。どんどん汚くなっていった。
もちろん親にはこっぴどく叱られた。そりゃそうだろう。カバーと言えど高級品だ。しかもうちのは(あの当時では)一般的な赤のベルベット調のではなく、シルクでできたちょっといいやつだったのだ。
傍から見れば、理解に苦しむというか、単なる奇行にしか見えなかっただろう。
なんだろう・・・曲がったもの、位置がずれたものが見れない、小学生の時はこれがひどかった。例えば曲がったまま貼ってしまったポスターとか。
貼り直せるものは問題ないけど、頑丈な粘着テープで貼ってしまったとか、貼り直しできないものが厄介だった。
一度、大きな壁掛けフックをタンスに貼ろうとして、曲がったまま取り付けてしまった。
これがどうしても剥がせなくて、苦し紛れの解決策が、家にあった印刷用紙を上から被せて貼り付け、曲がったフックを見えなくしてしまおうというものだった。
タンスの正面にでかい紙を貼り付けている(しかも中央が盛り上がってて何かを覆ってる感じバレバレ)・・・、なかなかに妙ちきりんな光景だったようで、見る人見る人に「これは何?」と聞かれた(小学生当時、習っていたピアノの先生の事情で、家をピアノ教室として貸し出しており、家には人の出入りが多くあったのだ)。
そういう無理やり?な解決法をよくしていた。とにかく見えなくできればよかったのだ。
もうひとつ自分の中で印象的だったのは、中学に入学してすぐの時。
新しく下ろしたノートに「数学」「英語」などのタイトルを書くのだけど、なぜかこの時、異様な気負いがあった。これからずっと使うノートの表紙にふさわしい、完璧に満足のいく理想的な字にしなければいけないと。
いざ書こうと思ってペン先をノートに近づけると、手がぶるぶる震えてきてとても書けそうにない。
「なんで震えるの!」と自分にイラついてきて勢いで書いたら全然不満足な出来となった。
しかしボールペンで書いたものだから消せない。ボールペン字も消せる消しゴムというのを使ってみたが、紙がこすれるだけで完全には消えない。どんどん汚くなっていく。手を加えれば加えるほど汚くなっていく。
春の陽気が差し込む穏やかな日曜の午後、一人部屋の中で身をよじらせて発狂寸前になっていた。
それまで生きてきた中で最大級のストレスかと思うくらいだった。
何度もしつこく書いた部分をこするうちに、とうとう表面がめくれて破れてしまった。一番表のビニール部分が剥がれ、毛羽立っていた。そしてビニールとともに文字も剥がれて消えた。
しかも毛羽立ちのおかげで、元のツルツル面より安定して書きやすくなっていた。そのおかげで今度は満足いくように書けて、なんとか気は収まった。
同じ頃、授業中、うっかり真新しい綺麗な教科書に折れ目をつけてしまい、やはり授業どころではなくなった。
反対側に折り返すことで折り目をフラットにしようと試みたり、家に帰ってアイロンを当ててみたりしたけど、折り目が消えてなくなることはない。折れた紙は絶対元通りにはならない。
苦しまぎれに考えついたのが、折り目を鉛筆でなぞって、折り目じゃなく「模様」にしてしまおう、というものだった。
我ながら「なんて無理やりな」とは思ったが、鉛筆で折れ目に線を引いてみると、「鉛筆の線」であって折れ目ではないように見えた。それで何とか気は収まった。