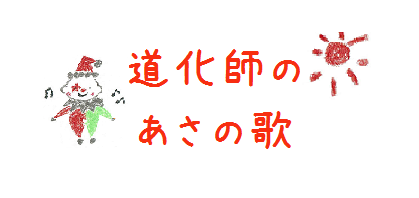「過保護」という言葉は昔からよく使われる。
私も何か買ってもらったり何でも親にやってもらったりして、よく「過保護に育てられてね~」と言われた。
その言葉は、過ぎた保護をしたがる親ではなく、子供である自分に向けられていると感じた。
親が過保護に”ならざるを得ない”くらい、甘ったれで何にもできない子なんだね~親御さんは大変ですね~って感じで。
たまに明らかに親が言われてると分かる時でも、やはりそれを聞いた私自身もとても傷つくのだった。
過保護と言うと、なんでも子供の言うことを聞く、子供の思うままにさせるというイメージがあるけど、実態は「何でもしてあげる=何でも手出ししてくる」で、私が手を出す前にすでに親の手が出ているし、頼んでないのに、むしろして欲しくない、自分でやりたいのに、先回りしてやってあるし、あ~あ~危ないからそんなことするんじゃない!どれ、お母さんがやってあげるから!ってなるともう、人の言葉なんか耳に入らなくなる。
それに対し、言葉にならない気持ちが渦巻くこともあれば、「やらせた方が楽だなウシシ」となることもあった。20代になるまで、家のこととか本当に何もしなかったし。
要は子供の「自立」は全然考えていない親だった。
何でもしてあげるのは全部自分のため。自分がやった方が手っ取り早いし、汚されたくないし、危なっかしい手つきの子供を見て、ハラハラ・ドキドキしたくないのだ。
子供が自分ひとりでできなくて、恥をかいたり、将来困ったりすることなんか、全然考えていない。
それどころか稀に、親が「できないに決まってる」と思っていることを私が易々とこなしでもすれば、親として喜ぶどころか「オモシロくない…」という感じだった。
子供が親を頼ることで、親が自分の自尊心や支配欲を満たすのだ。
まぁそれでも…そういった行動から愛情を感じ取ることも(ごく幼い頃に限っては)多々あったのも事実で、「愛されている」と子供の頃いっぱい感じられたことは、形はどうあれ、ありがたいことであるとも思うが…。
物はあれこれ買い与えられた。
私もねだることはよくあったし、買ってもらえると嬉しかった。
私が小学校3年生の時だっただろうか。
当時、CDが出初めの頃で、家にはCDを再生できる機器(CDラジカセ)がなかったのに、母親と買い物に出かけた際、私はレコード店でCDをねだって、買ってもらった。
でも当時は曲が聞きたかったというより、可愛いアイドルが印刷されたCDのジャケットに思わず惹かれただけで、買っても聴けないことは何となく承知していたし、CDラジカセを買ってと言った記憶もない。
ところがその当日だったか次の日だったか、家に突然、CDラジカセが置かれていたのだ。
感激より驚きの方が大きかったというか、さすがに子供の私も「こんなの買ってもらっちゃっていいのか…?」みたいな感情がわいた。
子供のおもちゃレベルのものではなく、本格的な、むちゃくちゃ高そうな、高機能なものだったから…。
父は家電製品好き、特にAV機器マニアで、家には当時最先端の再生機器やでかいスピーカーがたくさんあった。
DVDが出始めでまだちょっと珍しかった頃も、父はいち早くDVDプレーヤーを手に入れていた。
普及すれば安くなるけど、まだ出始めの頃であったのと、ソニーの最先端の高機能なやつで、当時20万くらいしたものだった。
同年代の子からは、あまり色々と物を持っていると、嫉妬の感情を買った。
そのうち、「買ってもらうこと」にコンプレックスを抱くようになり、何か買ってもらっても、友達が家に来た時などにはそれを隠すようになった。
こうして周囲から、何でも欲しいがまま、過保護という烙印?を押された私だが、「何でも買ってもらえた」は事実かというと、そうは言い難く。。
なんていうのかな、おもちゃとか漫画とか、文具類とか、子供らしいもの、あるいは親の趣味趣向に合致するものは喜々として買ってくれたが、成長の証的なもの?は、なぜか絶対に買ってくれないということが多かった。
例えば思春期になった時のブラジャーとか。部屋で1人で寝るためのベッドとか。
どちらかと言うと、本当に必要なものを買ってもらえなくて苦労した経験の方が多い。
過保護と過干渉はどちらか一方というのは少なく、多くがセットになっているんじゃないだろうか。
他人の目が関係することでは過干渉。例えば子供の振る舞いなどによって親が恥をかく、自分の体面が関係することにおいては、そりゃもう命がけで干渉(笑)。
人の目がない場所では、むちゃくちゃ甘やかす。というか、めんどくさいから何でも親がやっちゃう、めんどくさいから注意しない。
過保護とか過干渉というか、要は究極の自分本意なのだ。