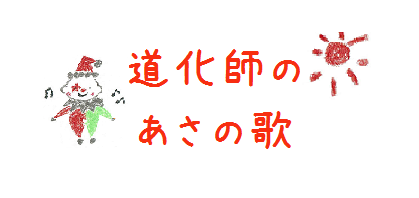小学校に上がっても、新たな火種が勃発した。
時間割を調べて、明日の授業に必要な教科書や持ち物をランドセルに入れる、小学校に上がれば誰もが経験する、自己管理の訓練の第一歩だと思う。
これも入学して最初の数ヶ月までだったか、もっと後までだったかは忘れたが、母親が全部やっていた。私もされるがままだった。
それが、周囲の友達に感化され、こういうのは自分でやるもんだということに徐々に気づいていったのか、ある日の夜母に、「私も今日から自分でやる」と言ってみた。
本当にそれくらい自分でできると思ったし、寝る間際の忙しい時間に母にやってもらうことに少し気が引けてもいた。
「自分でやる」と言えばむしろ喜ばれる、褒められると、懲りもせず思っていた。
返事は、とりつくしまもなく却下。「絶対にダメ」の一点張り。
母の言い分は一貫して「私が自分でやったら忘れ物をするから」だった。
そう言われれば、そんな気もする。強く否定はできない。
でもじゃあ、いつになったら自分でやれるのか、「まだ無理だからさせない」ではなく、「自分でできるようになる」ために「自分でやる」という経験を積んでいくんじゃないのか、当時ここまで言葉にして言えたわけじゃないけど、子供の頭でもそれくらいのことは思った。
本気で母親の言い分が理解できず、いくら必死にこっちの気持ちを訴えても、話がまったく噛み合わない。分かっているのにはぐらかされてる感じもした。
この時ばかりは私も頑張った。泣いてわめいての大げんかになった。声を枯らして訴えた。
それでやっと母が折れたのだ。
でもしぶしぶというか、「じゃあ勝手にしろ」という感じだったので、後味の悪い気分が残った。
何より、ここまで必死に訴えないと「明日の授業準備を自分でする」ということもできないのかと、愕然としたのを覚えている。
今まで何となくだったのが、「自分の親は異常かも」とはっきり意識した初めての瞬間だったと思う。
自分でやるようになって、母の言ったとおり、忘れ物は増えた。
忘れ物をして先生に叱られたりクラスメイトに笑われるたびに、やっぱり親の言う通りだったのか、自分は授業準備すら満足にできないのかと落ち込んだ。
また、そのことを母に知れたら「それみたことか」と思われて、「やっぱりお母さんがやってあげなくちゃダメ」ということになる。
「絶対にやれる」「忘れ物なんかしない!」と言い張って自分でやるようになった手前もあり、母の前では万事上手くやれているフリをした。
確かに私は注意力が足りなくてうっかりミスが多い。おっちょこちょいだし、しっかりしていない。親から見ればさぞや危なっかしくて頼りない存在だったかもしれない。
それを全部「育て方」のせいにするつもりはないけど、
私は自分のことを自分でするという体験が乏しかった。上手くいくかいかないかではなく、「まずやってみる」という体験がなかった。
最初は穴だらけの出来栄えでも、失敗しても、それを忍耐強く見守ってくれて、やがてできるようになるという健全な過程をほとんど経験していない。一から十まで全部自分でやってしまいたくなる。私の存在を無視して自分の手が動いている。
それは、私が元から信頼されるような人間じゃないから、よその子より劣っているから、不甲斐ないから、どうしたってそんな風に考えるようになる。
でもそれは、私が信頼されない人間だったのではなく、「自分の子供を信じて見守ることができない」という母自身の問題だった、そのことに気づいて、ほんの少し自尊心を回復させられるまでには、かなりの紆余曲折を要した。