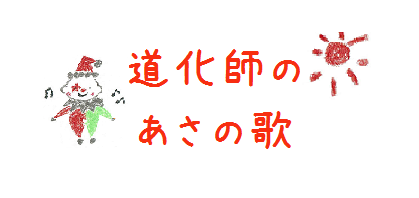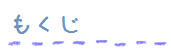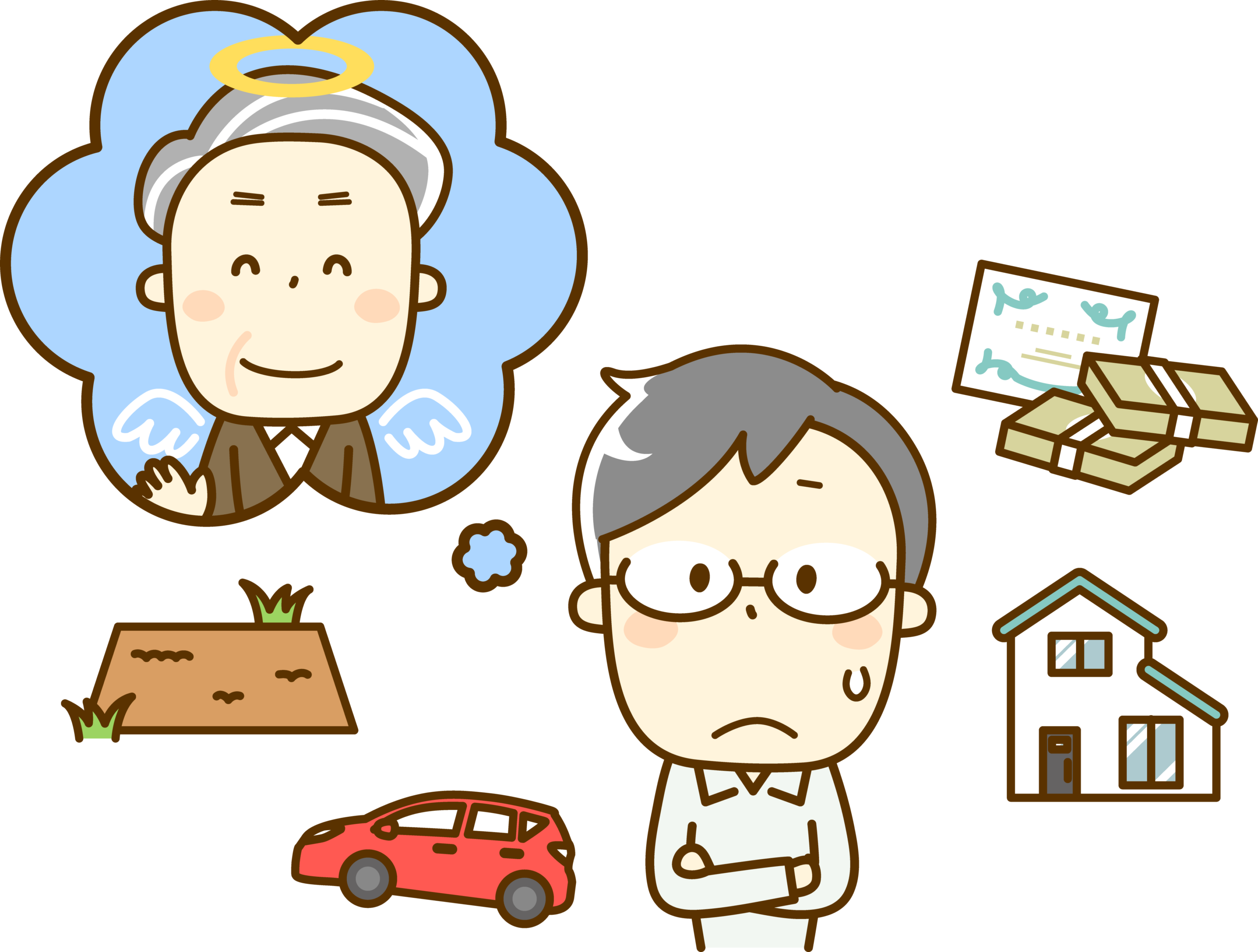 私の父親は、私がまだ引きこもりから脱する前に亡くなった。
私の父親は、私がまだ引きこもりから脱する前に亡くなった。
父親72歳、私が35歳の時だった。
引きこもりの人にとって「親が亡くなる」というのはまぁ・・・「一大事」だろう。
憎んでいようと恨んでいようとどんなに仲の悪い親であっても、親に衣食住すべての面倒を見てもらっている引きこもりが大半だろうから。
その日常が、覆されてしまう。
引きこもりの人々にとって最も恐れる大きな「変化」が待っている。
色々なことが、「今のままでいい」というわけにはいかなくなる。
一口に「引きこもり」と言っても親との関係は色々だろうけど、
悲しみ、罪悪感、憎しみなどの感情に浸る間もなく、さまざまな手続きを迫られる。
我が家の場合、亡くなった父親は、家のすべての金銭的面倒を見てくれていた。
母親は専業主婦。子の私はほとんど社会に出たことのない長期引きこもりの無職。
私達母子は右も左も分からない世間知らずだった。
私も母も、生活の維持、公的な手続き等のすべてを父親任せにしていた。
父が危ないと分かった時の私は、
ふよう(扶養)って何?
控除・・・くうじょ??(正解:こうじょ)
ってレベルだった。
年金のこと、保険のこと、何もかもよく分かってなかった。
母も母で、一人で銀行の窓口に行ったこともなければ自分でATMでお金をおろすこともできない。
それでもなんでも、これからは自分たちでやっていかなくてはならいのだ。
幸い「知識」の面は、インターネットで調べることでラクラク身につけることができた。
ちょろっと検索にかければ何でもわかりやすく載っていて、本当に便利でありがたい時代だなぁと思う。
もしネットがない時代だったらどうなっていたことか。きっとどうすることもできず右往左往しながら青ざめていただことろうと思う。
最近は「終活」という言葉もよく耳にするように、本屋に行けば、身内が亡くなったときにやるべきことや、相続の話などが分かりやすく解説された本がたくさんある。(昔からあったのかな?引きこもってたのでよく分からない)
あと我が家の場合、父がすごく几帳面で細かすぎるほど何でも記録する人だったので、幸い家計や資産の実情はすぐに把握することができた。
事前準備
まず事前準備として、
実印
がない人は、作っておこう。
実印とは、
役所のデータベースに印影が登録されている印鑑のこと。
実印には大きさなど様々な決まりがあるけど、
どこのはんこ屋さんでも、「実印用の印鑑作りたいんですけど」と言えば、適したはんこを作ってくれると思う。
印鑑を作ったら、印鑑登録をして(上に書いた印影をデータベースに登録する作業)、印鑑登録証というカードを作ってもらおう。
相続の書類など法的な書類に使う印鑑はこの「印鑑登録された印鑑」(=実印)でなければならない。
役所の住民票とか受け取れるところで作ってもらえる。
ついでに役所に来たら、
相続(亡くなった人の資産を遺族の口座等に移動させる)の際、必ず求められる書類を一通り取っておこう。
まずは、
亡くなった人(被相続人)の、
生まれてから亡くなるまですべての戸籍謄本(こせきとうほん)
「戸籍謄本」と聞くと、「離婚するとここに×がつくんだよー」という白い紙に達筆の手書きの紙をイメージしていたけど、今はそういうのじゃないんだね。電子化された薄ピンクの紙になっている(自治体によって違うかも?)。
このように戸籍謄本の様式は何度か「改製」を繰り返している。
銀行や生命保険会社などから故人の遺産を移動(相続)する際どこでも、「戸籍謄本を用意して下さい。それも、生まれてから亡くなるまですべての」と言われた。
この、”生まれてから亡くなるまですべての”という意味が最初分からず、最新の戸籍謄本だけを持っていっても、「これだけではダメです」と突っぱねられた。
すべてって?戸籍謄本は1つじゃないの?と思ったが、そうではないようだ。
改製前の昔の様式を改製原戸籍(かいせいげん・かいせいはらこせき)と言うらしい。
つまりは、そういった改製前の戸籍謄本も「すべて」用意しろということなのだ。
具体的には被相続人(故人)の、戸籍謄本(最新の)、改製原戸籍(改製前の戸籍謄本)、除籍謄本、住民票除票。
すべては亡くなった人(被相続人)の財産を受ける権利がある人の存在をもれなく確認するためなのだろう。
戸籍謄本は改製を行っても前の内容がすべて新しいものに写されるわけではなく、省略される内容もあるため(以前の結婚歴やその子供の存在など結構重要なものも!)、また除籍謄本というものにも、最新の戸籍謄本に載っていない内容が記されていることもあるため、これらすべての謄本が必要になるようだ。
銀行とか保険会社の人にその辺りのことを詳しく聞いても、若い人だとあまり分かっていなかったりもするので、詳しいことは役所に質問しよう。
とにかく「相続のために必要なので、生まれてから亡くなるまですべての戸籍謄本をください」と言えば、伝わると思う。
あとは、相続人(相続を受ける人)全員の戸籍謄本(これは最新のだけでよい)と、印鑑登録証明証。
相続人の戸籍謄本に関しては、私のように結婚していなく故人の戸籍謄本から抜けていない人はもちろん必要ない(親の戸籍と一緒だからね)。
印鑑登録証明証は、上で書いた実印を印鑑登録して印鑑登録証を作ると発行してもらえるもの。
印鑑登録証自体は滅多にそれ自体の提示を求められることはない(ので大切に保管しておこう)。
代わりに、「私は印鑑登録証を持っていますよ~」という証明になる、印鑑登録証明証というのを発行してもらえる(ややこしい…!)。これが相続手続きの際、求められることがあった。
さて、それでは私がやった手続きを順を追って説明していこうと思う。
健康保険関係
まず最初に手を付けたのが、健康保険証の作り直し。
と、それに伴う「世帯主」の変更届出。
通夜葬儀などが一通り終わり、親せきなども帰った次の日、
母がベランダの軒先で転んで頭を打った。
すぐに病院へ行って事なきを得たが、
その時に提出した保険証は、父が世帯主名義のままのものだった。特に何もなくそのまま使えたのだけど。
ただこのように怪我や病気はいつくるかわからないので、
まず健康保険関係の手続きを一番先に済ませなければと思ったのだ。
我が家の場合、父は年金暮らしだったので健康保険の種類は国民健康保険(通称:国保)だった。専業主婦の母親も無職の私も当然国保。
国民健康保険の保険料は一家の世帯主に請求が行くため、保険証には世帯主の名前が記される。
今までは世帯主が父親だったので、世帯主の変更も届け出なければならない。
市役所の市民課、住民票の交付などをするところでやってもらえる。
年金
次にやったのが、
父がもらっていた年金の給付停止手続きと、今後母親の生活資金の重要なベースとなる遺族年金受給の手続き。
私はずっと、父がもらっていた年金にはどういう種類があるのかも知らなかった(というか年金にそんな色々種類があることも知らなかった)。
また夫に先立たれた母に遺族年金が支給されるというのも知らなかった。
父は大学卒業後から定年まで地方公務員として勤め、その後数年民間企業にもいたので、もらっていた年金の種類は3種類。
老齢共済年金(公務員が入る年金)
老齢厚生年金(民間企業で入る年金)
老齢基礎年金(国民が全員入る国民年金)
共済の方は電話連絡と郵送だけですべての手続きが済んだが、厚生年金の方は、数十キロ先の年金事務所に出向かなければならなかった。
共済年金については、
国家公務員ならこちらへ
https://www.kkr.or.jp/
地方公務員はこちらへ
https://ssl.shichousonren.or.jp/
基礎年金(国民年金)と厚生年金は最寄りの年金事務所へ
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
年金受給者が亡くなったことを伝えれば、
年金の給付停止手続きと同時に、(該当者がいれば)遺族年金、未支給年金の手続きも一緒にやってくれるはず。
必ず事前に赴く先の機関に電話をして、必要な書類等を確認してから行こう。
年金にはそれぞれ年金受給者が亡くなった場合、配偶者と子に遺族年金というものが用意されている。ただし配偶者であれば支給されるのは厚生年金と共済年金のみで、基礎年金は18歳以下の子がいる配偶者のみとなっている(非常にざっくりとした説明なので、詳しいことは年金事務所に問い合わせるか、もっと詳しい他のサイトを見てね)。
未支給年金について。
通常年金は2ヶ月に一度、偶数月に2ヶ月分まとめて支給されるが、後払い?というのか、例えば4月に支給される年金はその前月の「2月と3月分のもの」となる。
年金は亡くなった月の分までもらえる。1月に亡くなれば1月分までというように。
私の父は3月に亡くなったのだけど、3月分の年金は4月に支給されるので(2月分とまとめて)、亡くなった時点では「未支給」ということになる。これが未支給年金。
死亡日以降に故人に入ってくる収入はすべて「相続」の対象となるので、この未支給年金も相続の対象となってしまう。年金事務所にて相続手続きがすべて済んだあとで、相続者に振り込まれることになる。
すべての手続きが済むまで2~3ヶ月かかると言われ、我が家の場合、手続きをしたのが4月初旬で、未支給年金の振り込み、共済・厚生遺族年金支給が始まったのは6月だった。
銀行と保険会社に連絡
次に銀行と保険会社に連絡。
銀行は預金者死亡の報を聞きつけ次第すぐに口座を凍結する、という噂は聞いていたけど、そういうことはなかった。預金額にもよるのだろうか?地方の銀行だから?新聞の死亡欄にも名前は載せたんだけどね。
しかも…あまりおおっぴらには言えないけど、
亡くなった直後も、ちょくちょく父の口座からお金を引き出し続けた。
通夜葬儀、親戚へのもてなし、病院への支払い、その他諸々の出費、そして何よりその間も生活していかきゃいけないから生活費として。
なにせ我が家は残された遺族が引きこもりの無職と専業主婦だったので…。母も一応自分の銀行口座はあったが、お金の管理はすべて父親がやっていた。
銀行では、母と私(遺族)が「亡くなりました」と銀行窓口に出向いて伝えた時点で、「では今から凍結します」となった。
死亡日以降の出金(数十万くらい)が記帳された通帳も見せたが、特に何も言われなかった(うん百万単位の多額のお金だとアウトかもしれない)。
ライフラインの名義変更
そして忘れちゃいけないのが、
電気、ガス、水道、固定電話等のライフラインの名義変更。
電話で各契約先に連絡し、新しい名義人(我が家の場合は母親)と、支払い方法(銀行引き落としかクレジットカード払いなど)を伝えるだけで済んだ。
相続登記
故人の持ち家だった家に住み続ける場合、土地と家の名義変更も必要(相続登記)。
お金を払って司法書士にやってもらうこともできるけど、特に難しいこともなかったので、自分でやってみてもいいと思う。
必要書類(遺産分割協議書、戸籍謄本など)を持って管轄の登記所に行き、言われた手続きを行うだけで済んだ。
必要書類はこちらも事前に電話などで確認してから行こう。
なお手続きの際、登録免許税というお金を取られるので、キャッシュカードを持参して登記所に行こう(固定資産税評価額の1,000分の4)。
遺産分割協議書についてだけど、自分で作成することも可能だけど(ネット上にも書き方指南やテンプレートがあります)、我が家は税理士に頼んで作成してもらった。
我が家は相続税がかかるほどの資産はないし、法定相続人も母と私の二人だけというシンプルなケースだったけど、相続税が0円でも税務署に申告したかったのと、準確定申告が必要なるかどうかなど自分では判断できなかったので。
準確定申告とは、亡くなった日から、その亡くなった日の年の1月1日までさかのぼって、その期間の所得を申告するというもの。
会社員などで源泉徴収されていた(収入から税金を差し引かれている)人は必要ないけど、年金生活者などは必要になる。
ちなみに相続税は亡くなった日から10ヶ月以内、準確定申告は亡くなった日から4ヶ月以内という期限がある。
車関係の手続き
最後に手を付けたのが、父が所有していた車のこと。
父が亡くなった時、私は車の免許を持っていなかった。
車のことなんて法的なこと含め右も左も分からず(「廃車」ってどうすることなのかとか)、一番後回しでいいやと思っていた。
車はまだ比較的新しくきれいで走行距離も少なかったので、売るつもりではいた。私も(当時)すぐに免許を取るつもりだったが、父の車はマニュアル車なのだ。AT限定で免許を取る私は運転できない。その車を売って、AT車を買う資金にするつもりだった。
でもその時、他の相続手続きを進行しつつ、長期引きこもりから仕事を始め、自動車学校にも通い…、かなりハードな日々を送っていたので、緊急じゃない車のことまで頭が回らなかった。
「そう言えば車…!」と思い出したのは、卒検が終わった後のこと。
意外にも仮免も卒検も1回で通ってしまい、あとは運転免許試験所での試験を待つのみという時、そう言えば免許を取った後運転する車がまだないことに、ハタと気づいた。
慌ててネットで複数社に査定を申し込み、対人苦手の元長期引きこもりが頑張って値上げ交渉し、一番高く値を付けてくれたところに買い取ってもらった。1日で終わらせた!(4社くらい呼んだ)
なにせ元引きこもりで無知で世間知らずだったので、お金が振り込まれるまでは、騙されてるんじゃないかとか色々不安だった。
それから車を買いに走った(笑)。車なんてどこの何がいいとか全然分かんないから、父の車のメーカーの販売店に駆け込み、ちょうど気に入った中古車があったので、「じゃあこれで!」って(笑)。でも全然後悔とかなくて今現在もそれに乗っている(軽自動車)。同時に自動車保険も決めた。
今思えば大きいお金が動くことなのに、とにかくすべてを慌ただしく決めてしまい、よく失敗なく終われたなあと思う。
ちなみに自動車保険の等級だけど、
故人の等級は、家族の誰かが引き継げるって知ってました!?
私の場合、本来なら新規で保険に入った場合6等級からスタートなので保険料はべらぼうに高かったはずだけど、無事故で20等級だった父の等級を引き継げたおかげで、かなり安く済んだ。
亡くなった人と同居していたことが条件らしい。
保険会社に言えば、中断証明書というものを発行してもらえる。
この中断証明書があれば等級がそのまま保存され、保険会社を変えても等級をそのまま引き継ぐことができる。
その際、故人が乗っていた車の廃車が証明できる書類または車を売ったことが証明できる書類が必要と言われた。
以上、長くなってしまったけど、親が亡くなってからやった手続きのまとめでした。
最後に
正直、悲しむ間もなく手続きに追われ、まして仕事などの合間を縫ってこれらをやるのはかなり大変だと思う。
自分でやることが難しい人は、司法書士などに頼む(代行してやってくれる)という手もある。
絶対に親の遺体をそのまま放置してはだめ。
よく年金を不正受給するため親の遺体を隠したとか言われるけど、そうじゃないと思う。
たぶん、分からなすぎて、恐怖で、どうにもできなくて、そうなってしまうんだと思う。
何をどうしていいかわからない人は、引きこもり支援機関に電話しよう。
こればかりは、勇気を持ってやろう。
必ず手を差し伸べてくれる人がいるから。